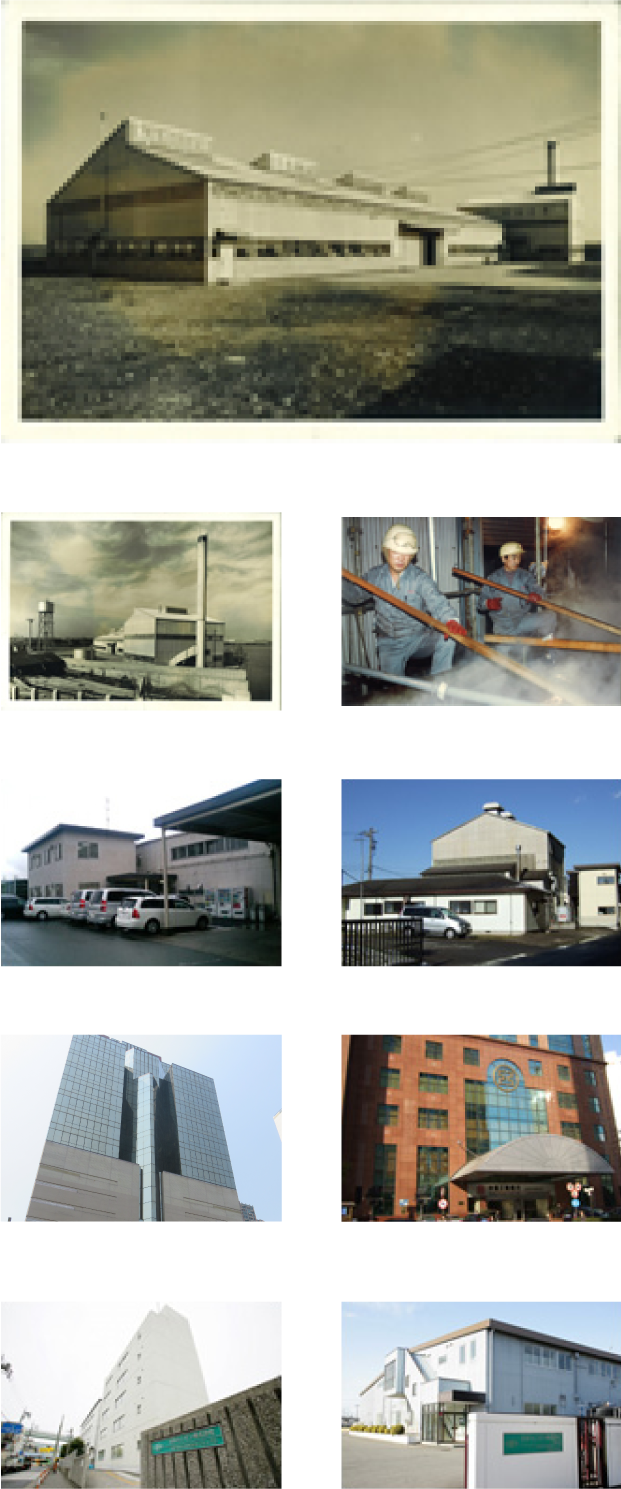1. 社名の由来
無電解ニッケルめっきの総称でもあり、当社の社名でもある「カニゼンめっき」(Kanigen®)は、C(K)atalytic(触媒)Nickel(ニッケル)Generation(生成)の頭文字をとり、Kanigenと命名されました。
カニゼンめっきとは、電気を使わずに化学反応によってニッケル燐合金をコーティングすることです。カニゼンめっきは、他のメッキと比較して、


等の特性があります。
その特性から、工業部品の機能を強化する機能めっきとして、自動車や半導体部品、デジカメやパソコンといった身近なものからF1マシン、ジェット機、人工衛星に至るまで幅広い分野で当社の技術が活きています。
当社の社名でもあるカニゼンが、無電解めっきの総称「カニゼンめっき」と言われるのもその証です。
2. カニゼンヒストリー
-
1.カニゼンめっきの発見
1944年、ドイツの化学者であるA.BrennerとG.Riddellは金属パイプ内面にニッケル-タングステン合金のめっきをする際、次亜リン酸塩を加えた電解液を用いたところ、金属管の内壁のみならず外壁にもめっきが付き、さらに電流効率が120%に達するといった異常現象を発見した。
さらにこの現象を研究したところ、電解によるものだけでなく次亜リン酸塩の還元作用によっても析出し、ある一定の溶液組成と条件の下で、化学的にめっき膜が形成されることが判明した。しかしながら、A.BrennerとG.Riddellの画期的な発見も、
① めっき速度が遅い
② めっき面が層状で均一性がない
③ めっき液が不安定で寿命が短い
④ コストが高い
等の問題から実用化されるには至らなかった。

-
2.カニゼンめっき実用化までの歩み
1947年、米国のGATC社のG.Gutzeitらが、A.BrennerとG.Riddellの発見したカニゼンめっき(無電解ニッケルめっき)の研究に着手し、EAST-CHICAGOのパイロットプラントにて研究を続けた結果、1952年についに現在のカニゼンめっき(無電解ニッケルめっき)を完成させた。

-
3.カニゼンの誕生
カニゼンめっき(無電解ニッケルめっき)の実用化に成功したGATC社は、米国内およびヨーロッパ・オーストラリア・日本にカニゼンめっきのライセンスを販売、当時の小野田セメント(現太平洋セメント)が日本におけるライセンスを取得し、1955年、日本カニゼン株式会社を設立した。